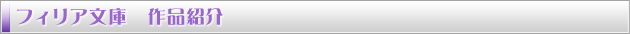アルカナ・ファミリア 〜見えない心〜【ミニドラマCD付き限定版】
目当ての人物は、食堂ですぐに捕まえることができた。
「ああ、お嬢様。巡回は終わりましたか、お疲れ様です」
いつも通り穏和な笑顔で、お茶の最中らしきルカがフェリチータを出迎えてくれた。
テーブルにはルカだけではなく、パーチェとデビトの姿もある。
「ちょうど、実験が一段落したところだったんですよ。そしたらこの人たちに捕まって、やれお茶を淹れろだの、パイを焼けだのと好き勝手に——」
「だぁって、おなか空いてたんだもん。いいじゃん、そのあとマーサがパン焼きすぎたって、山ほどくれたんだからさ」
パーチェは皿に並べられたパンをもりもりと口に運んでいる。時間的にはお昼を少し過ぎたばかりだが、多分これは昼食ではなく食後のデザートといったところだろう。
そして『山ほど』と表現している割に、皿の上にはあと数個しかパンが載っていないのは、パーチェがその山をほとんど崩した後だからだろう。
説明されなくても簡単に状況を読み取りつつ、フェリチータはルカに手招かれるまま彼の隣の椅子に腰を下ろした。
「お嬢様の分も、すぐにお茶を用意しますね」
ルカはいそいそとフェリチータの分の飲み物を支度し始めている。
「何だァ、どうしたバンビーナ、妙に思い詰めたような顔して」
こちらはお茶だけを口に運んでいるデビトが、からかうような調子でフェリチータに声をかけてきた。
「少し……ルカに聞きたいことがあって」
パーチェとデビトもいるならちょうどよかった。
フェリチータは、巡回中にあった老婦人と彼女の言葉について、三人に説明を試みる。
「——タロッコの力は人の手に余る、ですか」
最初はニコニコしながら、だがフェリチータの話が進むうちにその笑みを消したルカが、最後には表情を曇らせて口の中で呟いた。
「うん。ジョバンナっていう人は、そう言ってた」
「……」
ルカは考え込む顔で黙り込んでしまった。
フェリチータは少し不安な心地になって、その様子を見遣る。
ルカがジョバンナの言葉の意味を知っているのだと確信した。
手に余る、というジョバンナの言い回しからして、いいことではないのだろうと予測はしていたが、思っていた以上に重大なことなのかもしれない。
「ルカ、教えて」
少し強い調子でフェリチータは促した。
ルカが言い淀む様子なのは、フェリチータが知れば精神的な負担になることを懸念しているからだろう。
だったら余計、聞かないわけにはいかなかった。
「別にどうだっていいだろ、そんなもんは」
口を噤むルカに代わり、デビトがかったるそうに言った。
「聞いておもしろいもんじゃねェし、知ったところでバンビーナにはどうにもできねぇよ」
「デビトも知ってるんだ」
「……」
デビトは黙り込んでしまった。眉根がきつく寄っている。
「教えて」
フェリチータはデビトの方にも身を乗り出し、詰め寄った。
「チッ」
デビトは不機嫌な表情で舌を鳴らしただけで、フェリチータに答えようとはせず、荒っぽく椅子から立ち上がった。眼帯をした右目の辺りを掌で押さえている。
「ああ、頭痛ってェ。オレは昼寝でもしてくるゼ」
「デビト、待って」
デビトには答える気がないようだった。フェリチータの制止にも一切答える素振りを見せず、飲みかけのお茶を放り出して、さっさと部屋を出て行ってしまった。
「あーあ、もう、デビトは……ごめんね、お嬢」
申し訳なさそうに謝ったのは、パーチェ。眼鏡の奥の瞳を困ったように細めて、苦笑をフェリチータに向けてくる。
「でもおれも、わざわざお嬢が知らなくてもいいことだって思うよ」
「え……」
「ルカちゃん、お茶ごちそうさま」
パーチェまで、デビトのあとを追うように、その場を去ってしまった。
テーブルには、フェリチータとルカだけがぽつんと取り残される。
「……すみません、お嬢様」
二人の姿が消えた出入口の方を見遣っていたフェリチータの耳に、溜息交じりのルカの声が届いた。
フェリチータがルカに視線を戻すと、さっきのパーチェと同様、苦笑いをしている。
「あの二人にとって、あまり愉快な話題ではないんですよ。……私にもですが」
「……」
それでも教えて欲しい、と言うことに、フェリチータは躊躇した。
(別の人に聞いた方がいいのかな……)
ルカも、デビトも、パーチェも、話したくないし、教えたくない様子だ。
理由はわからない。
三人ともひどく心が揺らいでいるようだったから、もしかしたら【恋人たち】の力を使えば、彼らの考えを読み取ることはできたかも知れないが、フェリチータはそうしなかった。
してはいけない気がして、できなかった。
「何を、どこから、話せばいいものか……」
話を切り上げるべきか、食い下がるべきか、決めかねているフェリチータを見て、ルカの方からそう言った。
「ジョバンナさん、でしたか、お嬢様が会ったという不思議なおばあさん。もしかして占い師の方じゃないですか?」
「うん、そう言ってた」
頷いたフェリチータに、ルカが少しだけ懐かしそうに笑う。
「知ってる人? ルカのこと、『ルカ坊ちゃん』って呼んでた」
「ルカ坊ちゃんだなんて今も呼ぶのは、あの方だけですよ」
微妙に恥ずかしげに言ってから、ルカがもう一度溜息をついて、フェリチータを見返した。
「そうですね。あの頃の話は、まだお嬢様にはしていなかったかもしれません」
「あの頃……」
「はい。ジョバンナさん以外の人も、私のことをルカ坊ちゃんだなんて呼んでいた頃のことですよ。お嬢様が生まれるもっと前、マンマもまだ島に来る前の話です」
その頃を思い出す目になって話すルカを、フェリチータはじっとみつめて、言葉に聞き入る。
「当時のレガーロ島は、パーパの指導の下、ひとつにまとまっていました。ですが、どんなに島民がまとまっていても流行り病には敵いません。——そう、病魔が巣食い、島が荒れた時期があったんです」
今の平和な島しか知らないフェリチータには、その様子をうまく想像することができなかった。レガーロの人たちは、気候と同じように明るくて、いつも元気だ。
でもそうじゃない時期が、自分の生まれる前にあった。
「パーパの尽力に、珍しくジョーリィも医学的な知識を有効に活用して、ダンテは近隣の国から薬品や治療法を持ち込んでくれました。そして、島が落ち着いた頃、今度はパーパが疲労で倒れてしまったんです」
「パーパが……」
フェリチータは無意識に眉根を寄せて呟いた。
頷きを返すルカの表情には、だが暗い過去の思い出が蘇ったというよりも、なぜか少し呆れたような、なのにどこか感嘆するような、複雑な色が浮かんでいる。
「あの時のことは忘れられません」
「パーパが倒れた時のこと?」
「というよりも、倒れたパーパを心配して花を持っていった時のことです。パーパは私の手渡す花になんて目もくれず、いきなり叫びだしたんです。——『俺は旅に出る。それでいい女を連れ帰る。もう妻がいない生活には耐えられない!!』と」
「……」
ルカの声真似はまったくモンドに似ていなかったが、フェリチータはそう叫んだ時の父親の声が、何だかはっきりと想像できた。
スミレはモンドの二度目の妻だ。最初の結婚は、相手との死別で終わっている。流行り病で亡くなったそうだから、ルカの話してくれた『島の荒れていた時期』のことかもしれない。
だからフェリチータはモンドの前妻は当然のこと、彼女とモンドとの間に生まれたという異母兄弟とも会ったことがない。
「パーパの切迫した叫び声に、その場にいたジョーリィとダンテはすっかり呆れた様子でした。私は半分くらい感心してましたが……」
(本文P30〜38より抜粋)