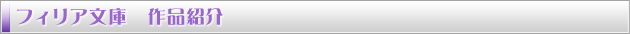最強の花婿、探してます! 花竜の王女と緑竜の騎士団
これでは本当に戦いが始まってしまう。リナが焦燥しながらキースの剣を持つ腕を?むと、ふっと、口許だけで微笑まれた。
「これはただの指導です。それに、私をその辺りにいる破落戸まがいと一緒にしないでもらいたい。あの馬鹿な子供に一筋たりとも傷はつけずに終わらせて見せますよ」
「でかい口叩くじゃねーか、おっさん」
「あなたも、そんな簡単に挑発に乗らないでください!」
「うるせーな、女は引っ込んでろ」
ヴィンセントに鬱陶しそうに言い放たれ、リナはさすがにかちんときた。さらに制止するために言い返そうとするが、ヴィンセントはもうリナには構わず、険呑な眼差しをキースの方へ戻した。
「つーか、オレだっていい加減あんたの口うるささにはうんざりしてたんだよ、キース。オレが一本取れたら、二度とこっちのすることにお説教しないでもらえる?」
「一本と言わず、私の髪一筋、服や皮膚の一枚でも傷をつけられたらそうしてやろう。どんなに小さな傷でもきちんと自己申告をしてやる」
「ふーん。あんたほんっとむかつく、っつーかー……——」
ヴィンセントが顔を伏せて笑い、肩を揺らした、と思った次の瞬間には、腰の剣を抜き放ちその場から駆け出していた。リナは驚いて息を呑む。まるで風のような素早さだった。そのまま流れるような動きで、キース目がけて片手剣の切っ先を繰り出す。
不意打ちの攻撃に、しかしキースはまるで怯む様子も驚いた顔も見せず、わずかに上体を逸らすだけでヴィンセントの剣を躱した。ヴィンセントの舌打ちが聞こえる。キースが身動き取れずにいれば、その前髪が一房落とされていたところだ。
ヴィンセントは休みなく剣を振り回した。キースは大剣の柄を両手で握り、体の前に刃を立て、その角度を少し変えるだけで、切れ間のないヴィンセントの攻撃を難なく受け流している。
(ヴィンセントという人の動きは速いけど、斬り込みが浅すぎる——それに、やっぱりキースさんの腕が、段違いだわ)
キースは一歩も動いていない。リナがすぐ後ろにいるので下がれない、というだけではなく、下がる必要もないのだろう。
ヴィンセントの剣は意外にもきちんと手入れされていたし、造りも上等だったが、まるで小さな子供が棒切れを振り回して大人に挑みかかり、軽くあしらわれているようにしか見えなかった。
「剣を狙って打ち込んでどうする」
息も切らさず、キースがヴィンセントを見下ろして言った。
「首か眉間か心臓を狙え。動けなくするために脚を薙ぐのもいい。何ひとつ形になっていないじゃないか」
キースの言うとおり、ヴィンセントは最初の一撃以降、相手の剣ばかりを狙って打ち込んでいる。剣を払うことが目的のようだが、怖がっているようにも見えた。威勢のいい言葉でキースに反抗したのに、人を傷つけることを怖れているのだ。
(まだ実戦の経験がないんだ)
どの程度の力を入れればどの程度の傷を与えられるか、魔物と戦ったことがあればある程度は把握できる。だがきっとヴィンセントは、命を懸けて崖っぷちで戦ったことがない。そういう太刀筋だった。
それに人同士の争いが禁じられているとはいえ、稽古が目的であれば真剣で手合わせすることも当然あるだろう。稽古をつける側がキースほどの使い手ならば、本気で斬り掛かったところで、相手に怪我をさせない方法で受けることはわかるはずだ。だがそれも理解できないくらい、とにかく経験が足りない。
剣伎だけではなく、体を鍛えること自体、本気で取り組んでいないのだろう。ヴィンセントはキースの爪先すら動かせないというのに、自分の方はもう肩で息をするような状態だった。
「こんなものか。予想よりももっと下だ」
「……っ」
キースが侮る口調で呟いたのを聞き止めて、睨みつける気の強さだけは、リナも感心するほどだったが。
「では——こちらから行く」
短く宣言して、キースが動いた。
「……!」
リナは思わず、両手を胸の前で組み合わせ、大きく鳴る心臓を強く押さえつける。慌てて距離を取ろうと後退ったヴィンセントの懐に、キースが瞬く間に飛び込んだ。
ヴィンセントの動きが風なら、キースのそれは嵐のようだった。ただ一歩踏み出しただけなのに、見ていたリナまで圧力を感じて後退りそうになる、気魄の塊のような動き。
「くっ」
そして地を薙ぐように下から振り上げられるキースの大剣を、ヴィンセントがそれでもどうにか剣で払いのけようと、反射的に柄を両手で持ち直し腰を落とした。
だが力の差は歴然すぎた。キン、と高い音を立てて、ヴィンセントの両手から剣が吹っ飛ぶ。剣はくるくると回りながら、いつの間にか離れたところで身を寄せ合って成り行きを見守っていたヴィンセントの仲間たちの方へと飛んでいき、彼らが悲鳴を上げながら散り散りに逃げていく。
ついでに、巻き込まれたくないとばかりに、姿が見えなくなる辺りまで全員走り去ってしまった。
「無様に尻餅でもつかなかったことは褒めてやる」
衝撃に痛むらしい利き腕の手首を押さえて呻くヴィンセントの鼻面へ、キースが大剣の切っ先を突きつけた。
(本文P53〜57より抜粋)